健康長寿ラボ
認知症の方や、介護に携わる方を含む社会が「認知症とつきあうために」はどうしたら良いのでしょうか?ここでは2つの興味深い事例を紹介します。
認知症カフェは1997年のオランダで開催されたアルツハイマー・カフェが源流ですが日本独自の広がりと深みを遂げています。日本では藤田医科大学の武地一先生が第一人者で「オレンジコモンズ」というNPOの理事長もされています。現在、日本で8000の認知症カフェがあるとのことです。日本の認知症施策である「オレンジプラン」の波に乗って、ここまで増えたと言えます。

図1.認知症カフェ(武地先生、左から2人目)
(藤田医科大学 武地一先生 ご提供)
認知症カフェは、月1回、平均2時間が多いようです(図1、文献1および2)。認知症カフェでは何をするのでしょうか?認知症カフェでは「認知症予防のための運動や脳トレをしない」というのがポイントなのだそうです。すなわち、「認知症と寄り添う」「認知症とつきあう」ということです。
認知症カフェでは、コーヒーを飲みながら、認知症とつきあう方法を模索する、考える、その人の人生のケース・バイ・ケースを楽しむ、といったことが行われています。この考え方は非常に重要と思われます。
もうひとつの興味深い取り組みをご紹介しましょう。
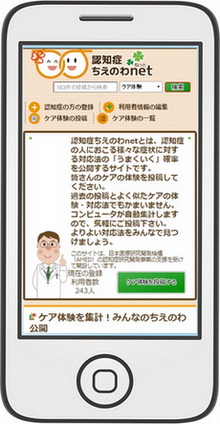
図2.スマホで認知症ちえのわnet
(高知大学 數井裕光先生 ご提供)
認知症の患者さんを介護するとき、困った、どうしたらいいの?という「とまどい」はだれもが持つものです。それに対して「こうしたら、解決できた!」ということをみんなで共有しましょう、というのが「認知症ちえのわnet」のコンセプトです。認知症ちえのわnetはウエブサイトで、認知症の人をケアする人がこんな困り事に対して、このように対応したら、「うまくいった」、あるいは「うまくいかなかった」という体験が投稿され共有できるようになっています(図2、文献3)。「検索窓」がありますので、「自動車運転の中止などの対応方法を知りたい」と入力すると、認知症ちえのわnetに収集された投稿の中から「自動車運転中止のためにケアする人がとった対応法」がポップアップされて閲覧できます。高知大学の數井裕光先生が中心となって行われている素晴らしい取り組みで、是非、覗いてみてください。
また認知症ちえのわnetには、「認知症対応方法発見チャート」というページもあります。ここには「物を盗られたと言う」、「介護を拒否する」などの場面と質問が設定されており、それぞれの質問にYesかNoかで回答していくと適切な対応法(案)に導かれるという仕組みです。どのような点に留意して対応法を選択するのかを楽しみながら知ることができます。
さらに「対応方法を教えて!!」というページもあります。認知症の人の行動に、どうしたらよいのかがわからない時に、ここに投稿しておくと、うまくいった対応法を知っている人が投稿を通して教えてくれるという仕組みです。
(文責)里直行、篠原充
![]()