プレスリリース
2025年9月9日
国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター
国立研究開発法人国立長寿医療研究センター(理事長:荒井秀典。以下 国立長寿医療研究センター)老年学・社会科学研究センター フレイル研究部の研究グループは、全国の75歳以上の高齢者を対象に、フレイル(注1)とヘルスリテラシー(注2)の詳細な関連について、web調査(注3)によるアンケートを実施しました。
日本のフレイルの有症率は65歳以上で7.4%ですが、75から79歳では10.0%、80から84歳では20.4%、85歳以上では35.1%の人がフレイルであると言われています。フレイル予防には、運動をして体力を落とさないようにしたり、栄養のある食事を摂ったり、あるいは病気になった時に早めに対処することが重要です。
近年、ヘルスリテラシーが注目されています。フレイルの高齢者はヘルスリテラシーが低いことが報告されており、ヘルスリテラシーを高めることはフレイル予防につながる可能性があります。しかし、具体的にヘルスリテラシーのどのような能力がフレイルと関連しているか明らかになっていませんでした。
本研究では、フレイルの判定は「後期高齢者の質問票」(別添1)、ヘルスリテラシーは「HLS-EU-Q47」という質問票(別添2)を用いて、フレイルとヘルスリテラシーの関連を詳細に調べました。
本調査では、全国の75歳以上で要支援認定や要介護認定を受けていない高齢者、1032名(男性50.2%)から回答が得られました。回答者のうち、30.8%の方がフレイルであると判定されました。フレイルの人のヘルスリテラシーの点数は27点、フレイルではない人のヘルスリテラシーの点数は31点で、フレイルの人はヘルスリテラシーの点数が低い結果でした。これは、これまで言われてきた結果と同様でした。さらに、ヘルスリテラシーの47項目とフレイルの関連を調べた結果、フレイルの人はフレイルではない人に比べて、特に、以下の3つの健康情報を入手することが困難であるという分析結果でした。
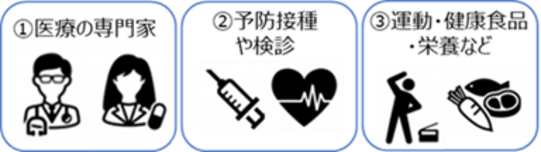
フレイルの人の点数(27点)はフレイルではない人の点数(31点)よりも、統計学的に明らかに低いことが分かりました。
※ 調査対象者の主観に基づく多変量ロジスティック回帰分析(注4)より
という多変量ロジスティック回帰分析の結果でした。
フレイルと健康情報の明確な因果関係については、さらなる研究が必要です。しかし本研究から、より多くの健康情報を入手することは大切であることが分かりました。
地域に住まわれている方々には、早いうちから健康に関する知識(ヘルスリテラシー)を高めること、自治体や企業の方々には、対象となる方々に対して、こうした情報へのアクセスをサポートすることが、フレイル予防の糸口になる可能性が示唆されました。
Hori N, Li J, Osuka Y.(堀紀子、李嘉琦、大須賀洋祐)


老年学・社会科学研究センター フレイル研究部 堀紀子、大須賀洋祐
電話 0562(46)2311(代表) E-mail:nhori@ncgg.go.jp、osuka@ncgg.go.jp
国立長寿医療研究センター総務部総務課 総務係長(広報担当)
住所 474-8511 愛知県大府市森岡町七丁目430番地
電話 0562(46)2311(代表) E-mail:webadmin@ncgg.go.jp
注)迷惑メール防止を目的に@を全角で表示しています。メールをお送りの際は@を半角に置換えてください。
![]()